病院情報の公表
令和6年度 函館脳神経外科病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 14 | 18 | 32 | 90 | 190 | 322 | 622 | 512 | 162 |
令和6年6月1日から令和7年5月31日に当院を退院された患者さんを年代別に集計しています。(年齢は入院時の年齢)
※「-」は10症例未満
当院は急性期の病床を有し、24時間365日の救急対応を行っています。
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)は、高齢の方に発症することが多く、日本人の死因で第4位を占める病気です。
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が危険因子となることから、60歳以上の高齢者で脳卒中の発生率が高くなります。
当院でも60歳以上の割合が、全体の82%を占めています。年代別では70歳代が約30%と最も多く、次に80歳代、60歳代と続いています。
※「-」は10症例未満
当院は急性期の病床を有し、24時間365日の救急対応を行っています。
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)は、高齢の方に発症することが多く、日本人の死因で第4位を占める病気です。
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が危険因子となることから、60歳以上の高齢者で脳卒中の発生率が高くなります。
当院でも60歳以上の割合が、全体の82%を占めています。年代別では70歳代が約30%と最も多く、次に80歳代、60歳代と続いています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 352 | 27.94 | 16.89 | 14.20 | 73.30 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 153 | 23.87 | 16.94 | 20.26 | 83.37 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 103 | 4.07 | 4.67 | 0.00 | 70.29 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 99 | 15.86 | 9.83 | 4.04 | 76.53 | |
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり | 88 | 2.00 | 2.86 | 0.00 | 64.66 |
脳神経外科の入院患者さんを疾患別に集計し、上位5つを挙げています。
当院では、脳卒中をはじめ、頭部外傷、脳腫瘍、脳動脈瘤など、さまざまな脳の疾患に対して幅広く診断、治療を行っています。
その中でも、脳梗塞は最も症例数が多く、内科的治療、脳血管内治療、外科的治療を病態に応じ組み合わせて治療を行っています。
さらに、発症早期からのリハビリテーションを実施し、日曜祝日も休むことなく365日のリハビリテーションを行っています。
また、頭痛やめまいの検査で偶然未破裂脳動脈瘤が発見されることもあります。その場合には必要に応じカテーテルを用いた脳血管撮影検査をして、治療適応を決定しています。
開頭手術で治療させて頂く場合もありますが、できる限り、患者さんにとって身体的に負担の少ない脳血管内治療(コイル塞栓術やフローダイバーター手術など)を行う方針にしています。
平均在院日数が全国平均より長くなっていますが、当院は脳神経外科の専門病院であるため、重症度の高い患者さんを多く診ている影響だと考えられます。
当院では、脳卒中をはじめ、頭部外傷、脳腫瘍、脳動脈瘤など、さまざまな脳の疾患に対して幅広く診断、治療を行っています。
その中でも、脳梗塞は最も症例数が多く、内科的治療、脳血管内治療、外科的治療を病態に応じ組み合わせて治療を行っています。
さらに、発症早期からのリハビリテーションを実施し、日曜祝日も休むことなく365日のリハビリテーションを行っています。
また、頭痛やめまいの検査で偶然未破裂脳動脈瘤が発見されることもあります。その場合には必要に応じカテーテルを用いた脳血管撮影検査をして、治療適応を決定しています。
開頭手術で治療させて頂く場合もありますが、できる限り、患者さんにとって身体的に負担の少ない脳血管内治療(コイル塞栓術やフローダイバーター手術など)を行う方針にしています。
平均在院日数が全国平均より長くなっていますが、当院は脳神経外科の専門病院であるため、重症度の高い患者さんを多く診ている影響だと考えられます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | ||
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | ||
5大癌と呼ばれる胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌の治療目的で入院された患者さんを集計しています。
※「-」は10症例未満
TNM分類とは、国際対がん連合により定められた癌の進行度を分類する方法です。
当院は脳神経外科の患者さんを主に診療しているため、いずれも10症例未満でした。
当院での検査等で専門外の疾患が疑われた場合には、地域の専門医療機関を紹介しております。
※「-」は10症例未満
TNM分類とは、国際対がん連合により定められた癌の進行度を分類する方法です。
当院は脳神経外科の患者さんを主に診療しているため、いずれも10症例未満でした。
当院での検査等で専門外の疾患が疑われた場合には、地域の専門医療機関を紹介しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | - | - | - |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
市中肺炎の治療目的で入院された患者さんを集計しています。
※「-」は10症例未満
市中肺炎とは、病院以外で日常生活をしていた方が肺炎になられた症例で、入院中に発症した肺炎は含まれておりません。
当院では、脳卒中の後遺症で通院されている患者さんが肺炎を併発して、入院治療が必要になるケースがあります。
令和6年6月1日から令和7年5月31日の間では中等症に分類される患者さんが1件、重症に分類される患者さんが2件、超重症に分類される患者さんが1件でした。
※「-」は10症例未満
市中肺炎とは、病院以外で日常生活をしていた方が肺炎になられた症例で、入院中に発症した肺炎は含まれておりません。
当院では、脳卒中の後遺症で通院されている患者さんが肺炎を併発して、入院治療が必要になるケースがあります。
令和6年6月1日から令和7年5月31日の間では中等症に分類される患者さんが1件、重症に分類される患者さんが2件、超重症に分類される患者さんが1件でした。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 634 | 31.65 | 76.76 | 16.52 |
| その他 | 62 | 38.10 | 78.06 | 1.87 |
脳梗塞の治療目的に入院された患者さんについて、患者数・平均在院日数・平均年齢・転院率を集計しています。
脳梗塞とは脳の血管が詰まることにより、脳細胞が障害を受ける病気です。症状は、意識障害、手足の麻痺、言語障害(呂律が回らない、言葉が出てこない)などが突然発生します。
脳梗塞を起こして早期に適切な治療を受けることが出来れば、後遺症が残らない可能性が高まるため、一刻も早く治療を受けることが重要な病気です。
当院は脳神経外科の救急病院に指定されており、24時間体制で患者さんの受け入れを行っています。
脳梗塞の患者さんの約9割が発症3日以内に治療を受けています。
患者さんの病状や脳梗塞の種類、発症からの時間などにあわせて、t-PA静注療法(血栓溶解療法)や脳内血管内治療(超急性期再開通療法)などの先進的な治療を取り入れ、迅速かつ高度な医療を提供しています。
2023年に新設された回復期リハビリテーション病棟では、生活機能の改善と、自宅や社会復帰を目指して集中的なリハビリテーションを行っており、退院後のより良い生活を目指して支援を行っています。
脳梗塞とは脳の血管が詰まることにより、脳細胞が障害を受ける病気です。症状は、意識障害、手足の麻痺、言語障害(呂律が回らない、言葉が出てこない)などが突然発生します。
脳梗塞を起こして早期に適切な治療を受けることが出来れば、後遺症が残らない可能性が高まるため、一刻も早く治療を受けることが重要な病気です。
当院は脳神経外科の救急病院に指定されており、24時間体制で患者さんの受け入れを行っています。
脳梗塞の患者さんの約9割が発症3日以内に治療を受けています。
患者さんの病状や脳梗塞の種類、発症からの時間などにあわせて、t-PA静注療法(血栓溶解療法)や脳内血管内治療(超急性期再開通療法)などの先進的な治療を取り入れ、迅速かつ高度な医療を提供しています。
2023年に新設された回復期リハビリテーション病棟では、生活機能の改善と、自宅や社会復帰を目指して集中的なリハビリテーションを行っており、退院後のより良い生活を目指して支援を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 86 | 0.48 | 15.95 | 3.49 | 77.28 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 50 | 1.90 | 13.70 | 2.00 | 66.80 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 47 | 1.23 | 29.15 | 6.38 | 65.17 | |
| K080-42 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの)(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの) | 40 | 1.00 | 12.15 | 52.50 | 69.20 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 39 | 1.08 | 31.18 | 5.13 | 70.85 |
脳神経外科で実施した手術を集計し、上位5つを挙げています。
当院で最も多く行われた手術は慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。これは、頭部打撲後通常1~2ヶ月かけて脳と頭蓋骨の間に血腫が溜まることで、脳を圧迫し、頭痛、物忘れ、手足の麻痺などが生じます。その溜まった血腫を取り除く手術です。
次いで、頚椎や腰椎の脊柱管狭窄症に対して神経の圧迫を取り除くために行う椎弓形成術が多くなっています。
そのほかに、くも膜下出血やその原因となる脳動脈瘤の破裂を防ぐため、脳動脈瘤の根本を遮断するクリッピング術や、コイルを用いて行う脳血管内手術など、脳血管疾患をはじめとした多くの症例に対して手術を行っています。
他医療機関との連携も行っており、他院医師による整形外科の手術も積極的に行っております。
当院で最も多く行われた手術は慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術です。これは、頭部打撲後通常1~2ヶ月かけて脳と頭蓋骨の間に血腫が溜まることで、脳を圧迫し、頭痛、物忘れ、手足の麻痺などが生じます。その溜まった血腫を取り除く手術です。
次いで、頚椎や腰椎の脊柱管狭窄症に対して神経の圧迫を取り除くために行う椎弓形成術が多くなっています。
そのほかに、くも膜下出血やその原因となる脳動脈瘤の破裂を防ぐため、脳動脈瘤の根本を遮断するクリッピング術や、コイルを用いて行う脳血管内手術など、脳血管疾患をはじめとした多くの症例に対して手術を行っています。
他医療機関との連携も行っており、他院医師による整形外科の手術も積極的に行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
入院中に医療費を最も要した傷病名と入院の原因となった傷病名が同一か異なるかを集計しています。
※「-」は10症例未満
上記にある疾患は重症な感染症や手術による合併症としてみられるものです。
今年度は入院中に敗血症を発症し、治療を要した症例が1件、手術・処置等の合併症が原因で入院した症例が9件でした。
手術・処置等の合併症には、水頭症におけるシャントの機能不全(詰まり)、術後血腫、手術創部の感染などがあります。
合併症が発生した場合には、迅速・適切に治療を行ってまいります。
※「-」は10症例未満
上記にある疾患は重症な感染症や手術による合併症としてみられるものです。
今年度は入院中に敗血症を発症し、治療を要した症例が1件、手術・処置等の合併症が原因で入院した症例が9件でした。
手術・処置等の合併症には、水頭症におけるシャントの機能不全(詰まり)、術後血腫、手術創部の感染などがあります。
合併症が発生した場合には、迅速・適切に治療を行ってまいります。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 166 | 166 | 100.00% |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 33.33% |
血液培養を行った患者さんのうち、2セット採取を実施した方の割合を集計しています。
血液培養は、本来無菌である患者さんの血液から病原体(細菌や真菌など)を検出・培養する検査です。
敗血症などの感染症の診断に用いられ、適切な治療方針の決定や感染源の特定に役立ちます。
血液培養には大きく分けて2種類あり、好気性菌を検出するための好気培養と嫌気性菌を検出するための嫌気培養があります。
血液培養は好気培養と嫌気培養の2つで1セットとされており、同時に2セット採取することで検査結果の精度が90%以上になると言われています。
血液培養は、本来無菌である患者さんの血液から病原体(細菌や真菌など)を検出・培養する検査です。
敗血症などの感染症の診断に用いられ、適切な治療方針の決定や感染源の特定に役立ちます。
血液培養には大きく分けて2種類あり、好気性菌を検出するための好気培養と嫌気性菌を検出するための嫌気培養があります。
血液培養は好気培養と嫌気培養の2つで1セットとされており、同時に2セット採取することで検査結果の精度が90%以上になると言われています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 71 | 47 | 66.20% |
広域スペクトル抗菌薬を使用した患者さんのうち、細菌培養を実施した方の割合を算出しています。
広域スペクトル抗菌薬は、多数の細菌を撃退するのに効果的な薬剤です。
細菌そのものは破壊しませんが、その代わりに細菌の成長と増殖を抑制して細菌の個体数を減少させます。
しかし、細菌の薬剤に対する耐性を発達させるという欠点があります。
そのため広域スペクトル抗菌薬を適正に使用するためには、細菌培養を行いどのような細菌が原因であるのかを調べることが重要であるとされています。
広域スペクトル抗菌薬は、多数の細菌を撃退するのに効果的な薬剤です。
細菌そのものは破壊しませんが、その代わりに細菌の成長と増殖を抑制して細菌の個体数を減少させます。
しかし、細菌の薬剤に対する耐性を発達させるという欠点があります。
そのため広域スペクトル抗菌薬を適正に使用するためには、細菌培養を行いどのような細菌が原因であるのかを調べることが重要であるとされています。
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 37589 | 93 | 2.47‰ |
入院中の転倒とベッドや車いすからの転落が発生した割合を集計しています。
転倒は複数の要因が重なって起こる重大な事故で、患者さんの回復や日常生活に大きな影響を与えます。
脳疾患によって手足に麻痺や感覚の障害が生じると、体のバランスを取ることが難しくなるうえ、視野が狭くなったり注意力が低下したりすると周囲を把握しにくくなります。
さらに、入院中の安静や長時間の臥床により筋力が低下すると、自分で身体を支える力が弱まり、転倒しやすくなってしまいます。
当院では、筋力・体力の低下をできるだけ軽減するため、発症早期よりリハビリテーションを開始しています。
同時に、患者さん一人ひとりの身体的状態を評価し、得られた情報を基に転倒リスクを数値化して看護計画に反映させています。
その上で、移動方法の検討や、移動時の声かけなど具体的な対策を行い、病棟スタッフやリハビリスタッフで綿密に情報を共有しながら、安全に療養できる環境づくりに努めています。
転倒は複数の要因が重なって起こる重大な事故で、患者さんの回復や日常生活に大きな影響を与えます。
脳疾患によって手足に麻痺や感覚の障害が生じると、体のバランスを取ることが難しくなるうえ、視野が狭くなったり注意力が低下したりすると周囲を把握しにくくなります。
さらに、入院中の安静や長時間の臥床により筋力が低下すると、自分で身体を支える力が弱まり、転倒しやすくなってしまいます。
当院では、筋力・体力の低下をできるだけ軽減するため、発症早期よりリハビリテーションを開始しています。
同時に、患者さん一人ひとりの身体的状態を評価し、得られた情報を基に転倒リスクを数値化して看護計画に反映させています。
その上で、移動方法の検討や、移動時の声かけなど具体的な対策を行い、病棟スタッフやリハビリスタッフで綿密に情報を共有しながら、安全に療養できる環境づくりに努めています。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
入院患者さんのうち、一過性ではあるものの、バイタルサインの急激な変化、人工呼吸器の使用、骨折、緊急手術、入院期間の延長など、高度な治療を必要とした転倒転落の割合を集計しています。
※「-」は10症例未満
令和6年6月1日から令和7年5月31日の発生数は4件でした。
このような転倒が発生しないように転倒防止対策を実施していますが、万が一発生した場合には、早急に適切な治療を行います。
さらに、転倒原因の分析、対策の立案を行い、その後の再評価を重ねることで再発防止に取り組んでいます。
※「-」は10症例未満
令和6年6月1日から令和7年5月31日の発生数は4件でした。
このような転倒が発生しないように転倒防止対策を実施していますが、万が一発生した場合には、早急に適切な治療を行います。
さらに、転倒原因の分析、対策の立案を行い、その後の再評価を重ねることで再発防止に取り組んでいます。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
手術を受けた患者さんのうち、開始前1時間以内にあらかじめ抗菌薬を投与した割合を集計しています。
※「-」は10症例未満
当院もガイドラインに従い、適正に投与を行っています。
※「-」は10症例未満
当院もガイドラインに従い、適正に投与を行っています。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 36669 | 53 | 0.14% |
入院中に発生した褥瘡で、深さがd2以上の発生率を集計しています。
褥瘡は、長時間にわたり同じ部位が圧迫されることで血流が悪化し、皮膚やその下の組織が壊死する慢性的な皮膚損傷です。
とくに寝たきりの方など体重が特定の部位に集中しやすい場合に発生しやすく、一般には「床ずれ」とも呼ばれます。
リスクの高い部位は仙骨やかかと、くるぶしで、栄養状態が不良の場合は褥瘡が発生しやすくなり、治癒に時間がかかる傾向があります。
当院では褥瘡対策委員会を設置し、褥瘡の予防体制の確立、治療に関する情報の収集とスタッフ向けの啓発教育活動を継続的に行っており、褥瘡の発生を未然に防ぐ体制を強化しています。
褥瘡は、長時間にわたり同じ部位が圧迫されることで血流が悪化し、皮膚やその下の組織が壊死する慢性的な皮膚損傷です。
とくに寝たきりの方など体重が特定の部位に集中しやすい場合に発生しやすく、一般には「床ずれ」とも呼ばれます。
リスクの高い部位は仙骨やかかと、くるぶしで、栄養状態が不良の場合は褥瘡が発生しやすくなり、治癒に時間がかかる傾向があります。
当院では褥瘡対策委員会を設置し、褥瘡の予防体制の確立、治療に関する情報の収集とスタッフ向けの啓発教育活動を継続的に行っており、褥瘡の発生を未然に防ぐ体制を強化しています。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1408 | 1101 | 78.20% |
65歳以上の入院患者さんのうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントを行った割合を集計しています。
入院早期に栄養アセスメントを行うことで、患者さんの栄養状態を総合的に把握し、低栄養リスクを発見して適切な栄養介入を行うことができます。
当院では、看護師、言語聴覚士、臨床検査技師、管理栄養士が連携し、栄養スクリーニングおよび嚥下機能評価を実施したうえで、患者さんの状態に応じた栄養管理計画を策定しています。
重度の低栄養例には栄養サポートチーム(NST)が介入して総合的な栄養改善を図っています。
入院早期に栄養アセスメントを行うことで、患者さんの栄養状態を総合的に把握し、低栄養リスクを発見して適切な栄養介入を行うことができます。
当院では、看護師、言語聴覚士、臨床検査技師、管理栄養士が連携し、栄養スクリーニングおよび嚥下機能評価を実施したうえで、患者さんの状態に応じた栄養管理計画を策定しています。
重度の低栄養例には栄養サポートチーム(NST)が介入して総合的な栄養改善を図っています。
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 37589 | 7606 | 20.23% |
入院患者さんのうち、身体的拘束を実施した割合を集計しています。
身体的拘束とは、抑制帯やミトン型手袋、衣服にクリップで留めるひも付きのセンサーなどを用いて一時的に身体の動きを抑制し、患者さんの行動を制限することを指します。
特に脳疾患などで意識や判断力が低下している場合には、ベッドや車椅子からの転落、手術後のチューブや点滴・栄養チューブの自己抜去、糞便に触れるなどの汚染行為、皮膚を掻きむしる自傷行為といった危険な行動を起こす可能性があります。
こうした行動による事故や怪我を防ぎ、患者さんの安全を確保するためには、やむを得ず身体的拘束が必要となる場合があります。
当院では、身体的拘束を最小限にとどめるために専任医師、専任看護師、医療安全管理室、薬剤師、理学療法士で構成される身体拘束最小化チームを設置しており、身体的拘束実施状況を継続的に把握し、代替的ケアの導入を検討しています。
さらに、尊厳を尊重した安全かつ非拘束的なケアの実践に努めています。
身体的拘束とは、抑制帯やミトン型手袋、衣服にクリップで留めるひも付きのセンサーなどを用いて一時的に身体の動きを抑制し、患者さんの行動を制限することを指します。
特に脳疾患などで意識や判断力が低下している場合には、ベッドや車椅子からの転落、手術後のチューブや点滴・栄養チューブの自己抜去、糞便に触れるなどの汚染行為、皮膚を掻きむしる自傷行為といった危険な行動を起こす可能性があります。
こうした行動による事故や怪我を防ぎ、患者さんの安全を確保するためには、やむを得ず身体的拘束が必要となる場合があります。
当院では、身体的拘束を最小限にとどめるために専任医師、専任看護師、医療安全管理室、薬剤師、理学療法士で構成される身体拘束最小化チームを設置しており、身体的拘束実施状況を継続的に把握し、代替的ケアの導入を検討しています。
さらに、尊厳を尊重した安全かつ非拘束的なケアの実践に努めています。
更新履歴
- 令和7年10月1日
- 初版作成
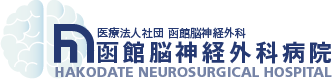
当院では手術を行う患者さんに肺血栓塞栓症の予防対策を実施しております。
肺血栓塞栓症とは肺動脈に血液の塊である血栓が詰まる病気で、エコノミークラス症候群としても知られています。
長い間一定の姿勢をとることにより下肢の静脈に形成された血栓が、肺まで運ばれることで肺血栓塞栓症を発症します。
発症すると突然の胸の痛み、息苦しさ、動悸、冷や汗などがみられ、血栓により血管が閉塞した範囲が広い場合、意識消失から最悪の場合は死に至ることもあります。